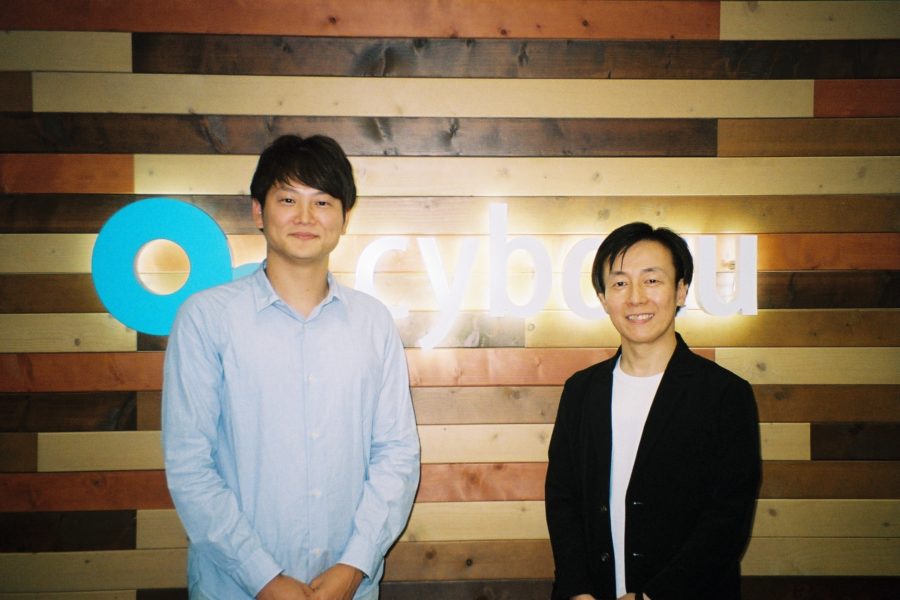OZ MEDIAオズビジョンを「外」と「中」から伝えるメディア
SEARCH
サイボウズ青野慶久社長と『ティール組織』をサカナにして話してみた。 真のティールはBeing、Doingへの果てなき挑戦に潜んでいた。
TOP対談 シリーズ「リソウノソシキへの旅」

『ティール組織』(フレデリック・ラルー著、鈴木立哉訳、2018英治出版)。「ビジネス書大賞2019」経営者賞など数々の賞を獲得し、一般書籍を含めてベストセラーとなったビジネス書である。この書籍に心を打たれた経営者は数多い。サイボウズ株式会社の代表取締役社長青野慶久もその一人である。
なぜティール組織に共鳴したのか。「いやあ『読んどいた方がいいですよ』って社員みんな言うもんでね。ひゃー600ページもあるのか参ったなって」。そう破顔しながらも冒頭のようにコメントする青野社長。「イイタイコトはこの本にある」。『ティール組織』についてそう語る青野社長に、ご自身の経営観への自信を新たになさったような感覚を持った。
2019年7月3日。『ティール組織』に唯一取り上げられた日本企業、株式会社オズビジョン。その代表取締役の鈴木良と青野社長が、日本橋に燦然とそびえるランドマーク「東京日本橋タワー」のサイボウズ社オフィスで初めての対談に臨んだ。そこには「アタマが良い」だけではたどり着けない地に足の着いたティール論が確かにあった。
ティール段階だから良いというわけではない。
試行錯誤から生まれる独自性にこそ価値がある。
愛媛県松山の2DKのマンションからスタートし、一代でサイボウズを東証一部上場、売上高113億円、経常利益11億円(共に2018年12月期)の堂々たる企業に育て上げた。規模だけではない。チームワークあふれる社会を創るという理想を掲げ、数多くのユニークな制度の導入をはじめ、ヒトが働くことそのものへの挑戦をしていることでも広く知られる会社である。その稀有な集団からは主力である優れたグループウェアのみならず、もはや公共性まで帯びているかのようなメディア「サイボウズ式」など優れたコンテンツが生み出されている。
一方で青野社長は言う。「今の当社はティールで言うところのオレンジ」。意味するのは、今のサイボウズは達成型組織の段階であり合理性や結果を出すことを主眼としている、ということ。その言葉だけを聞くとサイボウズが目指す在り方と少々違和があるように感じる。

「つまり作りたい社会、会社に向けての道標が手に入ったということです。ティールのような会社が私たちの目指すところなんだということですね。今はまだ至っていない」。ティール(色)の段階とはすなわち「進化する組織」であり、個々の意志が優先されビジョンや事業がその意志を基に変化、組織の存在目的に接近していく段階にある、ということを意味する。
「オレンジが必要な時にはオレンジを、ティールが必要な時はティールを。その時々の必要性に応じて必要な状態を引き出せるかどうかがほんとのティール。『ティール組織』を監修した嘉村賢州さんはそうおっしゃっています。たしかに仮に大災害が発生した時に、個々の意志を尊重し、ところであなたはどうなさいますか、なんてやってられません。即逃げろでしょ。特にIT業界ではレッド(注:トップが圧倒的な力をもって牽引する組織状態)やオレンジが必要な時もあります」。1997年の設立から20余年。きっとサイボウズにもさまざまなステージがあったに違いない。時に全社がレッドだったこともあっただろう。レッドあってこその今のサイボウズ、そう青野社長は感じているのではないだろうか。
オズビジョンも同様である。『ティール組織』で着目されたGood or New、Thanksdayの二つの施策は既に行われていない。「創業から時間がたつにつれて部署間での軋轢が生まれるようになりました。そこで組織を束ねる軸を創る必要性を感じた。その時出会ったのがマズローの欲求段階です。人の最高レベルの欲求段階は自己実現を果たすことであるとありこれだと思って企業理念に採り入れたんです。採り入れたからには徹底的に浸透だとばかりに、人事考課の半分に体現度合を反映したりとあれこれやりました。かなり強引に。そりゃ嫌気がさす社員も出てくるはずです。この時期に三分の一が退職するという経験もしました。その後も試行錯誤の連続」。鈴木社長の言葉を反芻すると、その時代のオズビジョンの実際の色はレッドもしくはアンバー(注:こはく色。軍隊的ヒエラルキー組織。規律を重視した思考により組織が拡大する状態)であったと思われる。その後も試行錯誤が続いたという。試行錯誤の一環として取り組んだのが前述のGood or NewでありThanksdayであったという。試行錯誤は絶え間なく行われるものであり、その営みにより企業は何かを経験し、その何かこそが独自性の源となっていくというのであれば。両氏が語ったキレイごとでは語りきれない各企業それぞれの苦闘と、そこから得た代替の効かない知恵にこそ価値があるのではないだろうか。

Beingに恥じる判断は致命的。
エピソードを通じてBeingを揺ぎ無き地盤にしていく重要性。
話はオズビジョンの企業理念に掲げられている自己実現というキーワードへと向かってゆく。「理念は石碑に刻むな」。この話題はそんな青野社長の言葉から広がっていった。
「鈴木社長はさきほど『理念は基本的に不変のものだと考えている』とおっしゃった。私は少し違っていて、不変としてしまうと変化が必要になったときに足枷になってしまうので可変と考えています。たとえば理念制定者が経営者であった場合、その経営者がなくなったときに、理念だけが後生大事にされている状態になり、たいていややこしいことになる。サイボウズでではないけれど実際にそんな体験もしました。だからサイボウズでは『理念2019』としている。年号がついている時点で変える気まんまん(笑)。しっくりきてないな、とか感じて変えることもあります」。
不変、可変、両者がおっしゃることは一見真逆のように見える。しかし話が深まるにつれて、両者の価値観の根源が見え隠れし始める。

「理念とは、繰り返し反芻するもの、しばしば戻っていける地盤のようなものだと私は考えているんです。その点で『浸透させること』は本当に重要だと考えてきました。唱和まではしませんでしたが、さっきも言ったようにいろいろな浸透策を試した。が、策に走れば走るほど反発を招く。ところがですね、あまり言わなくすると逆にああじゃないかこうじゃないかと彼らから言い始めるんですね。言われないからこそじぶんで考える。人の幸せとか自己実現とかはどちらかというと崇高な概念ですよね。崇高であるがゆえに叫べば叫ぶほどシラける、という感じ。たとえば人を採用するとき。会社にとって重大な意思決定となるわけですが、同じ能力を持つ二人のうち自分でどちらかを選ばないといけないとしたら。誰もがものすごく考える。そのとき判断軸として理念が台頭する。ユーザーや社員、すなわち人への貢献を人生の糧にできる人はどちらだろう。それを自己実現の糧と捉える人はどちらだろうと。言わないから、叫ばないから、ホンモノになる」。
「なるほど。鈴木さんの話を聞いていてBeingを大切になさっていると思いました。サイボウズの今の理念は『チームワークあふれる社会を創る』。『創る』ですからDoingなわけです。ところが社会を創ろうとしていると徐々に違和感が出てきたんです。Doすることはとても大事だけど俺達の在り方はどうなんだと。そこで社会の二文字をひっくり返して会社(=サイボウズ)と置き替えてやってきた。すると徐々にBeingが機能しはじめてきたんですね。そこでね、まさに鈴木さんがおっしゃるように自分で考え行動するという現象も出てくるんですよね。たとえば理念に関連していくつかキーワードを定めているんですが、その一つに『質問責任』というものがある。でですね、新入社員研修での話なんですけど、ある新人が研修中にヘッドフォンをしていたと。当然先輩が注意します。新人はなんと答えたか。『なぜヘッドフォンをしてはならないのでしょうか』と(笑)。ふざけんなばかやろう出ていけと普通なります。でもそこでぐっとこらえて考える。彼は質問責任をきちんと果たしている。聞けばちゃんと先輩がしゃべるときは外すし迷惑もかけてない。では質問責任に照らしてよしとすると。これね、ちょっとでも質問責任に照らして矛盾した言動をしたなら、この場合ふざけんなばかやろう出ていけとやったらだめでなんです。矛盾がまかりとおることだけは避けねばならない。Beingに恥じる判断は致命的です」。

青野さんのこのエピソードにはやられた。まさに我が意を得たり。人は人の行動にその人の在り方を見る。会社が人の集団である以上、集団としての行動の源であるBeingこそがまさに会社そのものだと感じる。鈴木社長もエピソードの重要性について語る。
「エピソードの威力は本当にすごい。エピソードとは具体的な事例であり端的に表れる判断基準そのものです。私も一つお話すると、社長なのでよく営業の電話がかかってくるんですね。その電話を受けた社員があるときこう言ってたんです。『今社長はいません』。これにものすごく違和感があって。嘘じゃないですか、俺ここにいるのに。会議で居ないならわかります。嘘じゃない。これを放置するのはよくない。『居ますが社長は電話に出ません』嘘じゃない。『忙しいので』嘘じゃない。『忙しそうにしているので』嘘じゃない(笑)。嘘だけはつかないでくれと。社長への営業の電話をシャットアウトするというのは一般的に大正解です。でもそれよりも大事なものがある。この一連の事例を通じてBeingがまた少し伝わることになります。最近面白い話があって。世の中大事な話はみんなエピソードなんじゃないかと思ったことがありまして。私の娘がミッションスクールに通っているんですが、それにあわせて私も毎週教会にいくようになりましてね。牧師さんの説教を聞きながらメモをとったりしているわけです。するとですね、説教ってエピソードの伝達なんだって。宗教ですから価値観や倫理観の話をするのかと思うんですが違うんですね。イエス様やその弟子がどこそこの町の誰それとこんな出来事にでくわしてこんな話をしてこうなった、と。エピソードを繰り返し話して牧師さんの思いや解釈を伝え腹落ちさせていく。100の説明より1つのエピソード。それが崇高な価値観をも浸透させていく強力な手段なんだと」。

自社らしく、自分らしく、心の底からワクワクしていけることを。(青野)
ワクワクしながら勝てることを。(鈴木)
「今オズビジョンは再び転換期を迎えています。自社や事業ごとのドメインの整理に入っているんです。今日青野社長とお会いできるということで、ぜひ聞いてみたかったのが、御社ではどうやってドメインを決めていかれたのか、という話です」。鈴木社長のこんな質問から本対談は終盤へと向かった。
「そうですねえ。『真剣に取り組めるものかどうか』っていうのが大事なような気がします。サイボウズはグループウェアを軸に商売を始めましたが、市場は横ばいだしライバルは強力。やがてM&Aをして複数企業を有するグループになっていくんですが、業績が下がったりしてくると興味関心さえ維持するのが難しくなっていく。だめだ、このままでは、って。そこで自分の内側から掛け値なしに出てくるような『本当に本当にやりたいこと』って何だろうって考えた。『やるからにはGoogleも脱帽するようなもの』ができるのは何だろうって考えた。結果、グループウェア一本でいこうと。この決定によってサイボウズを去っていく人も出ました。そりゃそうですよね、たくさんの領域で多彩な挑戦ができそうなサイボウズが、グループウェア専門店サイボウズになっちゃったんだから。一方で残ってくれた人は結果としてグループウェアで何とか生きたいっていう人たちだった。そういう人たちの集団になってそれがどんどん拡大していった。これはすごいことになるかも、というのが今です」。

「鈴木さんとのこれまでの話からすると、私たちサイボウズはDoingからBeingにいっていて、オズビジョンさんはBeingからDoingにいっているんだなと思いますね。サイボウズはドメイン決定が先でそのあと在り方に至った。御社は逆で在り方が先にあって今ドメインを整理しようとしている。さっきもお伝えしたサイボウズの今の理念は『チームワークあふれる社会を創る』です。あらゆるシーンでこれが軸となり、事業はどうする?研修はどうする?〇〇はどうする?〇〇はどうする?という風になっています。この軸に沿ってさえいれば、究極的には何をやってもいい。自分らしくやれればいいと言っています。逆にいうと何が生まれるかわからない。実は『サイボウズ式』もそんな感じで生まれたものの1つなんです。また、チームワークのためにはグループウェアというツールだけではなく、制度や風土改革も必要である。そう思うメンバーが社内で増えた結果、『チームワーク総研』という、サイボウズがこれまで挑戦してきたチームワークのための様々な取り組みを研修事業を通して企業や組織に提供するメソッド事業が立ち上がりました。これがまさにティール的と言えるんじゃないかと思っていますね。これから拡大する市場に着目して成長していくだけであったらそんなの簡単。他社でもできる。自社らしく、自分らしく、心の底からワクワクしていけることだけを選んで、その上で成長していくのは奇跡であり同時に難しいことです。難しいけれど今後もサイボウズはそういう会社で在り続けていきたいと思っています」。
「ドメイン整理の議論の中で1つだけ決めて臨んでいることがあるんです。『ワクワクしながら勝てることをやる』。これだけは自分の中で間違いないと確信している基準です。今お話を伺っていてその気持ちを新たにしました。これを軸にしてあとはいかにぜい肉を削ぎ落せるか。楽しみです」。